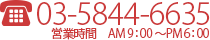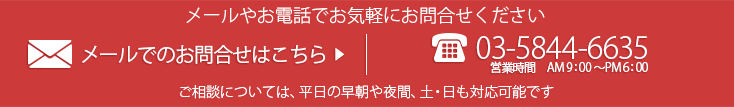両親がお元気なうちに、決めておきたいこと・・その4
昨年2018年の7月に民法改正がありました。この中に、特別寄与料に関しての改正がありました。
たとえば、夫の親の介護をした妻は、夫の親の相続人ではないので、従前であれば相続財産をもらうということは、考えにくいことでした。
ですが、相続人でない方(この場合だと、夫の親の介護をした妻)が介護や看護に貢献し、被相続人(この場合だと、夫の親)の財産の維持・増加などについて、特別の貢献(寄与)をした場合は、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。
現状では、特別寄与料の詳しい算定方法は決まっていません。
恐らく、介護にかけた時間×各県の最低賃金での計算であったり、介護のために辞めざるを得なかった仕事で本来もらえるはずだった給与、仮にヘルパーを雇った場合の費用相当額などが考慮されて、計算されるのではないかと言われています。
ただ、遺産分割の権利を持つ人が増えてしまうことになるので、相続人の親族間トラブルを増やしてしまう可能性もあり、よく考える必要があります。
ですが、義父母の介護を始めたときには、この特別寄与料を請求するかどうかにかかわらず、次のようなことを始めましょう!
★介護日誌をつけましょう!
介護をした時間や内容を介護日誌に記載しましょう。
通院のときのタクシー代や紙おむつ代など、介護費用を立て替えたときのレシートは捨てずにとっておきましょう!
★介護の状況を、親族と共有しましょう!
義父母が亡くなり、遺産分割などの話になったときに、「本当にあなたは介護をしていたのか?」「お金が欲しくて、適当なことを言っているではないのか?」と言われてしまうこともあります。
そういったことにならないように、親族には介護の状況をこまめに報告しておいた方がよいです。
★介護の前に、親族で義父母の財産の状況を確認し、共有しましょう!
介護のために義父母のお金を使ったのに、後から勝手に父や母のお金を使い込んだと言われて、揉めるケースも見られます。
最初に、一体義父母の財産がどのくらいあるのかを親族間で共有し、使ったお金はレシートなどの記録を残しておく等をしましょう。
トラブルになりそうなタネは事前に防いでおくことが必要です。
★介護のために退職した場合は、源泉徴収票を保管しておきましょう!
特別寄与料を出す際に、仕事を続けていた場合に得られるはずだった金額を算出すると言う方法も考えられます。
介護のためにお仕事を辞めた‥と言う場合は、源泉徴収票を無くさずに保管しておきましょう。
これらのことは、特別寄与料を請求しようと言う時に始めたのでは、手遅れ・・なことですので、早めに着手しておきたいものです。